2024年7月9日、専修大学経営研究所にて開催された講演会にお招きいただき、テーマ「生成AIの現在、そして課題」と題して登壇する機会を得ました。今回の講演は、私にとっても大変光栄な機会であると同時に、聴講される方全員が大学教授という、知識の深い方々の前で話すという重責を感じ、恐縮の念に堪えませんでした。
講演当日は、22名という多くの教授陣の方々にご参加いただき、熱意溢れる質疑応答が行われるなど、非常に充実した時間となりました。私自身、生成AIに関する最新の知見や、現状直面している課題について、普段ビジネスマン向けにお話ししている内容とは異なる角度からも議論が深まることを実感いたしました。
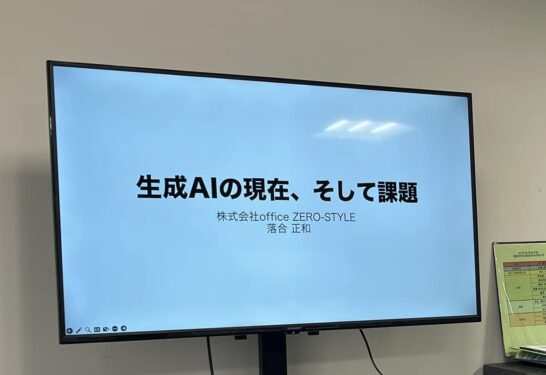
「生成AIの現在、そして課題」講演内容の概要
まず、講演では生成AIのこれまでの歴史と、その急速な発展について概説いたしました。生成AIは、ディープラーニング技術の革新により、テキスト、画像、さらには音声や動画の自動生成など、さまざまな分野で活用されるようになりました。しかし、その一方で、生成AIがもたらす倫理的、法的、技術的な課題も同時に顕在化している現状について、具体例を交えながらご説明いたしました。
また、生成AIの活用事例や、各種サービス・ツールの現状についても触れ、今後の発展可能性と共に、現実に直面する問題点についても解説いたしました。特に、生成AIの普及が進む一方で、コンテンツの信頼性や著作権、プライバシーの問題といった点において、解決すべき課題が山積していることを強調いたしました。
大変好評のご意見を頂戴し感謝申し上げます
当日は、話に熱が入り過ぎたためか、予定の時間を少々オーバーしてしまいました。時間配分について十分に配慮できなかったこと、深くお詫び申し上げます。それにもかかわらず、参加された教授陣の皆様からは、大変好評のご意見を頂戴し、講演内容に対する高い関心とご理解を感じることができました。こうした反響は、今後の活動の励みとなるとともに、さらなる情報発信の重要性を再認識させるものでした。
質疑応答における深い議論〜核融合発電と生成AIの関係〜
講演後の質疑応答では、普段のビジネスシーンではあまり触れることのない、より学術的かつ専門的な視点からの質問が数多く寄せられました。中でも、生成AIと電力需要との関連について、また核融合発電と生成AIの相互補完の可能性についてのご質問が印象的でした。
特に、核融合発電と生成AIの関係については、プリンストン大学の事例を引用しながら、超高温プラズマが突如として安定性を失い、核融合炉の磁場から逸脱する問題を、AIの活用によりいかに解決するかという具体的な事例を交えて解説いたしました。これにより、従来のエネルギー分野と最新技術との融合が、今後の持続可能な社会実現に向けた一つの重要なカギとなる可能性について、参加者の皆様と活発な議論を交わすことができました。
おわりに
今回の講演会では、生成AIの現状とそれに伴う課題について、教授陣の方々という厳しい目線の中で議論を深める貴重な機会をいただきました。私自身、話す内容に熱が入りすぎたあまり時間をオーバーしてしまうなど反省点もございましたが、多くの皆様から前向きなご意見を頂戴し、また深い質問を通じて新たな視点を得ることができました。
参加いただいた22名の教授の皆様には、今後とも生成AIに関する最新の知見や、技術がもたらす社会的インパクトについて、引き続き議論を深めていただければと願っております。私自身も、この貴重な機会を通じて得たフィードバックをもとに、さらに有意義な情報発信に努めてまいる所存です。
本日の講演が、生成AIに関する学問的理解と、実社会への応用を促進する一助となれば幸いです。今後も、時代の最先端を行く技術とその課題について、皆様と共に考えていく機会を大切にしてまいります。
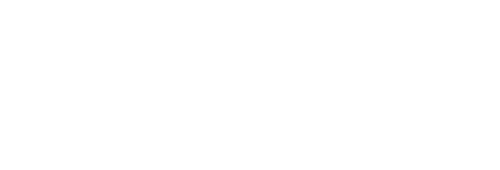







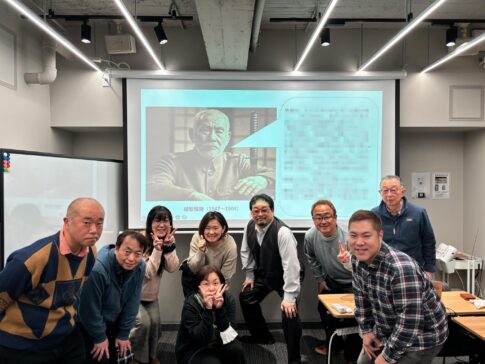

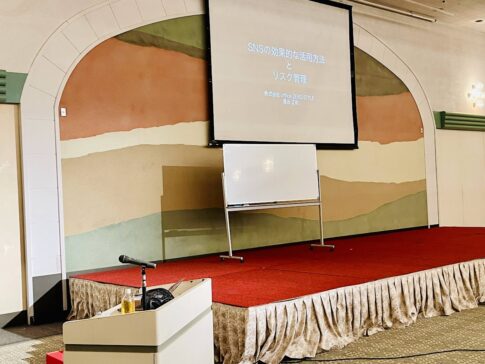
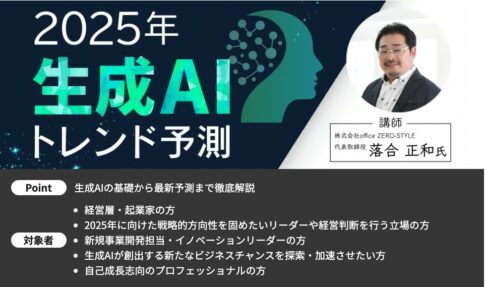



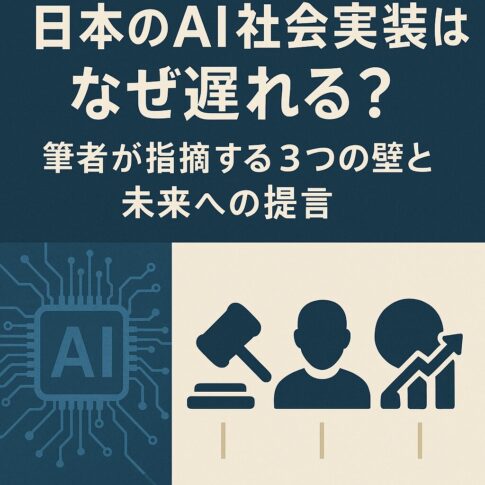
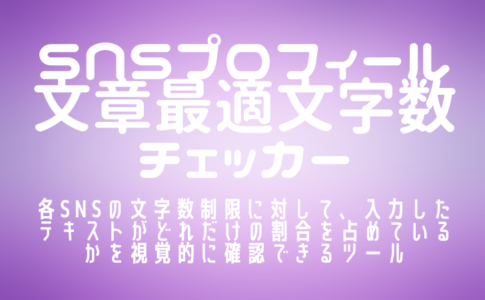
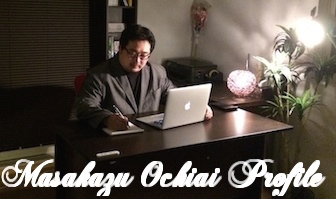
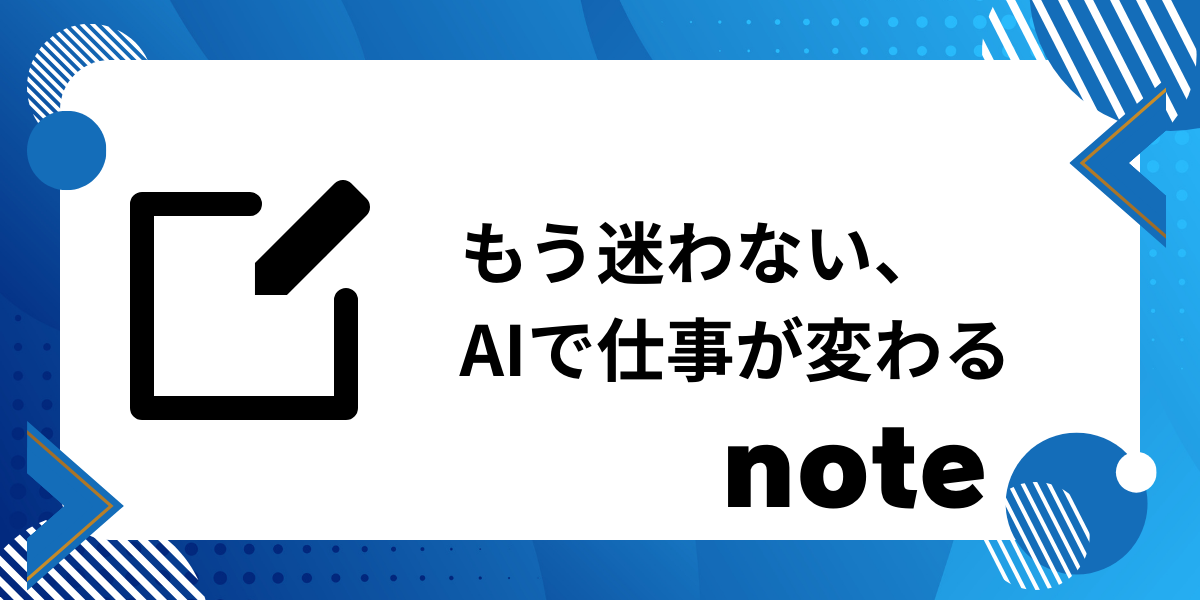




コメントを残す